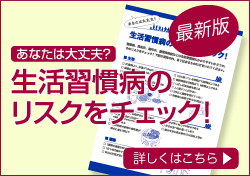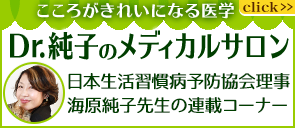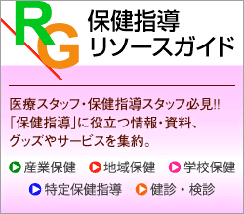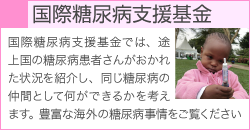2025年11月10日
11月14日は世界糖尿病デー 2025年は「糖尿病と職場」に焦点をあて、働く人が安心して過ごせる社会の実現へ
キーワード: 糖尿病

11月14日の「世界糖尿病デー(World Diabetes Day)」。2025年も国際糖尿病連合(IDF)が中心となり、啓発イベントが世界各地で行われる。
昨年に引き続き「糖尿病とウェルビーイング」をテーマにしているが、今年は特に「糖尿病と職場」1)に焦点をあて、糖尿病とともに働く人々を支える環境づくりや、社会全体での理解と行動を促すメッセージを強く発信している。
「世界糖尿病デー」とは
世界糖尿病デーは、糖尿病の予防や治療を続けることの重要性について多くの人に知ってもらうための日。2006年に国連が定めた世界的な啓発キャンペーンで、インスリンを発見したフレデリック・バンティング博士の誕生日にちなんで毎年11月14日2)に世界中で記念行事が行われる。
日本国内において糖尿病を持つ人と糖尿病予備軍を合わせた推定人数は、総人口の15%を超える約2,000万人と言われている2)。
糖尿病は、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が高い状態が続く病気であり、治療しなければ目や腎臓、神経などに障害を引き起こす可能性がある。さらに、心筋梗塞や脳梗塞などの命にかかわる病気との関連も深い。
重症化予防のためには早期発見・早期治療が重要だが、医療機関や健診で糖尿病といわれたことのある人の中で、「治療を受けていない」人の割合は、特に男性の40~49歳の働き盛り世代で最も高く、約5割が未受診または治療中断という状況だ。糖尿病には痛みなどの自覚症状が少ないことから、疑いがありながらそのまま治療を受けないケースが多くあることが、その要因と考えられている2)。
糖尿病を持つ人の10人に7人は働く世代
IDFの報告によると、世界の糖尿病を持つ人のうち約7割(4億1,200万人)は働く世代1)。この世代は、仕事の忙しさやストレス、外食、不規則な生活などによって血糖の管理が難しくなる傾向がある。また、治療を続けながら仕事を両立することに不安を抱えている人も多い。
今年の世界糖尿病デーで焦点をあてている「Diabetes and the workplace(糖尿病と職場)」というキャンペーンには、そうした現実を社会全体で支えようという思いが込められている。
糖尿病とともに働く人が直面する困難を打破するために
糖尿病を抱えて働く人々は、さまざまな課題に直面している。たとえば低血糖(血糖値が下がりすぎて体がだるくなったり、意識がもうろうとしたりする状態)が起きたとき、周囲に理解がないと休憩を取りにくい。そのまま意識を失うことがあれば、本人の命にかかわる。倒れたときに人にぶつかれば、相手がケガをする可能性もあるだろう。
また、通院や食事管理のために勤務時間を調整する必要があっても、職場の環境や人間関係によって遠慮してしまう場合もある。通院を中断すれば、薬がなくなって血糖管理ができなくなり、病状の悪化や合併症を発症するリスクが高まる。
さらに、「糖尿病であることを知られたくない」という心理的な負担も無視できない。就職や転職時には、糖尿病であることを伝えるか否か、そして伝えた場合には採用結果に影響が出る可能性など、悩みや心配が絶えない。採用後もスキルアップ、キャリアアップの機会を逃したり、ハラスメントやいじめを受けたりするケースもある。
こうした状況を改善・打破するには、同僚や上司が病気を理解し、糖尿病のある人を自然にサポートする体制が必要だ。企業は「病気を持つ人が治療を続けながら安心して働ける環境」を整えることが求められている。
職場・家族にできるサポート
糖尿病を抱えながら働く人を支えるには、職場と家族が糖尿病について理解を深めることが重要である。職場では、定期的な通院のための時間確保、食事や休憩の配慮、低血糖時に安全に対応できる仕組みづくりがなされることが望ましい。インスリン注射が必要な場合は、注射場所の確保も必要だ。しかしこうした業務上の配慮は、決して「特別なもの」ではなく、誰もが安心して働ける環境づくりの一部として考えられるべきだろう。
家族にできる支援としては、食事内容の工夫や生活リズムの調整、ストレス軽減のサポートなどが挙げられる。ときには「無理せず、焦らず、頑張りすぎないように見守る」ことも大切となる。
糖尿病の治療を続けながら、仕事やプライベートを充実させることは十分可能であるはずだ。社会全体が理解を深め、働く人が自分らしく生きられる環境を築くことが、世界糖尿病デー2025の目指す未来である。
参 考
1)Know more and do more for diabetes at work(IDF:国際糖尿病連合)
2)「世界糖尿病デー」について(World Diabetes Day committee in Japan)