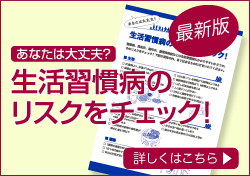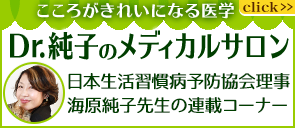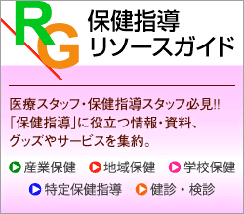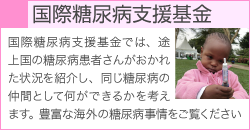2025年10月08日
10月8日は「糖をはかる日」
血糖変動の"見える化"が、生活習慣改善の鍵に
キーワード: 一無・二少・三多 糖尿病 健診・保健指導 協会からのお知らせ 協会・賛助会員関連ニュース

毎年10月8日は「糖をはかる日」です。この日は血糖の働きを正しく理解し、健康的な生活づくりに役立てるきっかけとなるように、2016年に制定されました※。
糖尿病と診断されていない方でも、日々の生活習慣によって「血糖値」は変動しています。食事内容や生活習慣などによって発生する、急激な「血糖変動」は、誰もが注意する必要があります。
「血糖値」「血糖変動」についての知識は、自分の身体を知ることにつながり、日々の暮らしの中で役立つ場面がたくさんあります。ぜひ、この「糖をはかる日」を機会に知識を深めてください!
※糖尿病治療研究会により制定。同会解散後は、日本生活習慣病予防協会で活動を継続しています。
血糖とは
血液中に含まれる糖質(ブドウ糖)のことで、血液によって全身に運ばれ、身体を構成する細胞のエネルギー源として重要な役割を果たしています。血液中の糖の濃度を示しているのが「血糖値」です。
「血糖変動」を意識する重要性
健康診断の結果票で「血糖値」「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」といった項目を目にする機会があると思います。
どちらも大切な指標ですが、血液中の「ヘモグロビン」というタンパク質に結合した「グルコース(ブドウ糖)」の割合を示す「HbA1c」は、過去1~2ヶ月の血糖の平均値を把握するうえで重要です。検査直前の食事や運動の影響を受けにくく、糖尿病の診断や長期的な血糖状態を把握することができるため、重要な検査項目として活用されています。
また、近年の研究では、HbA1cだけでは捉えきれない、急激な「血糖変動(血糖値の上がり下がり)」が、血管への負担となり、動脈硬化を進行させるリスクを高めることが明らかになっています。さらに、食後2時間以上経っても血糖値が低下せずに140mg/dL以上の高い値が続く「食後高血糖」も、重大な合併症の発症リスクを上昇させることがわかっています。
そのため、食事や運動、ストレスなどによって刻々と変化する「血糖変動」の把握が、2型糖尿病の予防や治療において重要視されています。
血糖変動を"見える化"する「CGM」

血糖変動を詳細に把握する技術「持続グルコース測定(CGM:Continuous Glucose Monitoring)」をご存知ですか?
CGMは、腕などに装着したセンサーで、皮下の間質液中のグルコース(ブドウ糖)濃度を継続的に測定するシステムです。専用のリーダーを使用したり、スマートフォンと連動させると、24時間365日の血糖変動がグラフで表示されます。
従来の血糖自己測定(SMBG)は、測定したタイミングの血糖値しか、わかりませんでした。CGMにより血糖変動が「点」ではなく「線」で見えるようになったことで、SMBGだけでは気づくことができなかった高血糖や低血糖を確認できるようになりました。

CGMによって得られる客観的なデータは、自分自身の身体と向き合い、生活習慣を改善するためのより具体的なヒントを得られる強力なツールとなります。
CGMの可能性 日常的に血糖が測定できる時代に
CGMは主に糖尿病でインスリン治療を行っている患者さんに保険適用されています。
糖尿病がない人が使う場合は保険適用にはなりませんが、使い捨てで10日間ほど使えるセンサーが1万円以内で購入できます(2025年10月現在)。CGMを使うことで日々の血糖値に対する意識が増し、特に糖尿病予備群といわれた方や、血糖が気になる方の健康管理に役立ちます。
さらに非侵襲的な血糖測定技術も続々と開発されており、今後はより多くの人々が日常的に血糖値を測定できる時代になるかもしれません。
ご自身の身体を知ることは、健康な未来を築くための第一歩です。「糖をはかる日」をきっかけに、自分自身の血糖値やHbA1cを確認してみませんか?
関連リンク
「糖をはかる日」公式サイト(日本生活習慣病予防協会ほか)
血糖トレンドの情報ファイル(糖尿病ネットワーク)
糖尿病3分間ラーニング「血糖トレンドとは」(糖尿病ネットワーク)
血糖トレンドを知る楽しさと、未来の健康な自分に向けて

コメント:山村 聡 先生(やさしい内科医のY's TV)
糖尿病内科医として、また血糖値実験ユーチューバーとして、日々の診療でお伝えしているのが、ご自身の「血糖トレンド」を知ることの重要性です。
長らく血糖値は、瞬間的な「点」でしか知ることができませんでしたが、フリースタイルリブレをはじめとする、比較的容易なCGM(持続グルコース測定)の登場により、血糖値の上がり下がりが連続性を持った「線」として「見える化」できるようになりました。これは、糖尿病の予防・治療において革命的な進歩です。
たとえば、健康診断でHbA1cや空腹時血糖値が問題なくても、食後の急激な血糖変動(食後高血糖)が血管に負担をかけ、動脈硬化のリスクを高めることが分かっています。この変動は、食事や運動、ストレスなど、日々の生活習慣と密接に結びついています。
ご自身の血糖変動を客観的なデータとして把握すれば、「あの食品を食べた後は血糖値が急上昇する」「食後に少し散歩すれば変動が穏やかになる」といった、具体的な生活改善のヒントが得られます。これは、食事の見直しを「正しく、そして楽しく」行うための強力なツールです。
10月8日「糖をはかる日」を機に、ぜひご自身の身体と向き合い、血糖トレンドを知る楽しさを想像していただき、できれば実践してみてください。その一歩が、10年後、20年後の健康な未来につながるはずです。
私のYouTubeチャンネル「やさしい内科医のY's TV」や、SNSでも、日々の血糖コントロールや糖尿病に関する情報をわかりやすく発信しています。「血糖値」「血糖変動」についてもっと知りたい方、日々の健康づくりのヒントを得たい方は、ぜひチェックしてみてください。
YouTubeチャンネル「やさしい内科医のY's TV」
X(旧・Twitter)「やさしい内科医 山村聡」
Instagram「やさしい内科医 山村聡/血糖値・糖尿病予防の専門家」
やさしい内科クリニック
「やさしい内科医のY's TV」おすすめ動画